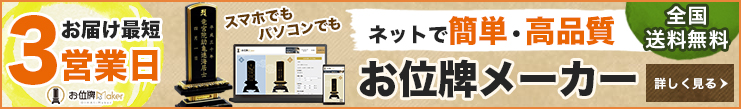位牌に刻む「戒名」は、故人様を供養する際に、お寺の僧侶から与えられる死後の名前です。
戒名入れは、依頼する場所や付ける名前によって、値段が大きく異なってきます。
しかし、「実際どれくらいの値段なのか?」「入れる名前の種類は?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、戒名入れの相場と安心して依頼するためのポイントを解説します。
位牌に記載する「戒名」とは?
位牌に記載する「戒名」とは、仏教において亡くなった方に与えられる死後の名前のことです。
正確には、亡くなった方が仏の弟子として修行を積む存在になったことを表します。
この戒名は、死後の安らかな成仏を願って僧侶によって授けられます。
もともと、戒名とは「出家した方が仏門に入るために修行僧として与えられる名前」でした。
しかし、仏教が中国から流入して以降、日本で独自の変化を遂げた結果、「亡くなった方」が仏弟子となり成仏を目指す象徴として与えられる名前へと変化しています。
戒名を入れる必要性
現在における日本の仏教では、亡くなった方のほとんどが戒名(法名)を授かる必要があります。
しかし、これは仏教の話であって、仏教徒でない場合は付ける必要はありません。
実際に日本の法律でも、「基本的に信教は自由」と定められていますので、無宗教や他宗教の方は、戒名を授かる必要はないのです。
また、位牌に戒名を付けない場合は、生前の名前を付けてもよいとされています。
ただし、生前の名前を付ける場合、お寺によって納骨を断られるケースがありますので、事前に確認しておくのがよいでしょう。
戒名の構造
位牌に記載される戒名の構造は、基本的に以下の順で記載されます。
|
「院号」 ↓ 「道号」 ↓ 「戒名」 ↓ 「位号」
|
ただし、宗派ごとに「梵字」や「法号」などが入ったり、文字の種類が異なったりするため注意が必要です。
宗派別の構造は以下のとおりです。
- 【真言宗】梵字+院号+道号+戒名+位号
- 【天台宗】院号+道号+戒名+位号
- 【浄土宗】院号+誉号+戒名+位号
- 【曹洞宗・臨済宗】院号+道号+戒名+位号
- 【日蓮宗】院号+道号+日号+位号
- 【浄土真宗】院号+釋号+法号
こちらをもとに、故人様の人柄や功績を加えたものが記載されます。
そのため、依頼する際は、故人様が生きていたときの人柄や功績をしっかり伝えることが大切です。
戒名はいつまでに入れる必要がある?
基本的に戒名は、故人様が亡くなられてから葬儀までに授けてもらいます。
そのため、短い期間で早めに依頼する必要があります。
なお、戒名はお世話になっている菩提寺の住職から授けてもらうものです。
菩提寺が遠いところにある場合でも、何かしらの対応はしてもらえますので、必ず一度連絡しましょう。
お世話になっている菩提寺がない場合は、葬儀社や仏壇仏具店に依頼します。
その際に寺院やお寺を紹介されますが、納骨先の確認が必要です。
これは、紹介された寺院やお寺と納骨先の宗派が異なると、戒名を変更する必要があったり、納骨を拒否される可能性があったりするからです。
また、場合によっては生きている間に与えてもらうケースもありますが、家族やお寺の住職が知らなかったとき、葬儀の際に新たな戒名を授かってしまいますので、生前に必ず伝える必要があります。
戒名入れの値段の相場と依頼先

位牌や墓石に刻む「戒名入れ」は、故人様を供養する上で重要な工程です。
しかし、どのくらいの費用がかかるのか、また具体的にどこに依頼すればよいのか、迷う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、戒名入れの値段の相場と依頼先について詳しく解説します。
戒名入れの値段の相場
戒名入れの値段の相場は、位牌の最後に記載される「位号(法号)」によって変わってきます。
位号(法号)は、いわば「◯◯様」のような尊称にあたる部分です。
性別や年齢、功績などに応じて階級が決められ、上位の階級ほど戒名の費用が高くなる仕組みです。
以下に「位号」の例と相場を記載しましたので、参考にしてください。
- 信士・信女:5万円~50万円
- 居士(こじ)・大姉(だいし):30万円~80万円
- 院信士・院信女:50万円~100万円
- 院居士・院大姉:100万円以上
注意点としては、依頼する場所や宗派、地域によって費用が異なってくることです。
そのため、事前にかかる費用を必ず聞いておくのがよいでしょう。
戒名入れの依頼先
戒名入れの依頼先は、まずお世話になっている菩提寺があるかどうかを調べます。
最近では、自分の家がどこの菩提寺と関わっているのか知らない方もいるため、分からない場合でも家族や親戚に聞くようにしましょう。
菩提寺がない場合は、葬儀社や仏壇仏具店に依頼するか、同じ宗派のお寺へ依頼します。
また、最近では、インターネットでも戒名を付けてくれるところが増えてきています。
手軽に依頼できる反面、対応する宗派や戒名の品質が異なる場合があるため、安心して任せられるかを慎重に判断し、依頼先を選ぶようにしましょう。
お位牌Makerでは、全45種類以上の豊富なバリエーションのお位牌をお客様のご要望に沿い、オーダーメイドで作成いたします。
さらに全国対応しており送料無料で、最短翌日にお届けいたします。
故人様を祀る大切なお位牌をぜひ、お位牌Makerにご依頼くださいませ。
戒名入れの際の注意点
戒名を入れてもらう際は、いくつか注意すべきポイントがあります。
故人様を適切に供養するためにも、しっかり確認していきましょう。
勝手に位の高い位号になっていないか確認する
戒名入れにかかる費用は、選ばれる位号によって大きく異なります。
そのため、依頼する際は、勝手に位の高い位号になっていないか確認する必要があります。
また、葬儀社や仏壇仏具店に依頼する際は、戒名入れを依頼されたお寺と納骨先の宗派も確認しましょう。
変更となった場合には、もちろん費用がかかってきますので注意しましょう。
使用を避けるべき文字がある
戒名には、使用を避けるべき文字があります。
例えば、以下の文字が挙げられます。
- 歴代天皇尊号
- 「昭和」「平成」「令和」といった年号
- 各宗派の祖師の戒名(法名)
- 蛙・犬・猫など、動物を表す漢字
- あまり使わない奇怪な難字
- 乃、也、於、但など無詮の空字
- 悩・狂・病・争・恥・敵・悩・死・狂・病など不穏の異字
なお、「麟・龍・鳳・鶴・駿・亀・鹿」など、めでたい動物を表す漢字は、使用可能です。
菩提寺の有無を確認する
冒頭でお伝えしたとおり、戒名入れの依頼では、お世話になっている菩提寺があるかどうかを確認する必要があります。
基本的に菩提寺には先祖が眠っていますので、葬儀後は菩提寺のお墓に入ることが一般的です。
しかし、お世話になっている菩提寺があることを知らず、ほかのお寺や寺院で戒名入れを行ってしまうと、菩提寺に納骨できなくなる可能性があるため注意しましょう。
戒名入れにかかる値段を確認しておく

戒名入れの正確な値段は決まっていません。
しかし、ある程度の目安はありますので、依頼する前に値段を把握しておくとよいでしょう。
白木位牌か写真を持参
白木位牌から本位牌へ移す際の戒名入れは、白木位牌を直接持参するか、白木位牌の表と裏の写真を撮って依頼先に渡しておくのがおすすめです。
戒名入れを依頼する際に、メモ書きを渡す方もいますが、戒名の文字は宗派によって大きく異なり、間違えやすいので注意が必要です。
そのため、戒名が書かれた白木位牌や写真などを事前に渡しておくと安心できます。
また、先祖の位牌があれば、それも一緒に持参すると、宗派が分かりスムーズに依頼できるでしょう。
まとめ
本記事では、位牌に記載する「戒名」について解説し、戒名入れの値段や依頼先を紹介しました。
戒名入れの値段は、戒名の最後に入れる「位号(法号)」や依頼する場所、宗派などによって異なってきます。
依頼する際は、事前に費用を確認しておくことをおすすめします。
また、依頼先は、お世話になっている菩提寺があるかを確認し、ない場合は葬儀社や仏壇仏具店に依頼しましょう。
ただし、葬儀社や仏壇仏具店に依頼する場合は、納骨先と宗派が同じであるかを確認する必要があります。
もし、近くに葬儀社や仏壇仏具店がない場合は、お位牌Makerのご利用がおすすめです。
お位牌Makerでは、全45種類以上の豊富なバリエーションのお位牌をサイト上のみで、オーダーメイドで作成いたします。
さらに全国対応しており送料無料で、最短翌日にお届けいたします。
故人様を祀る大切なお位牌をぜひ、お位牌Makerにご依頼くださいませ。