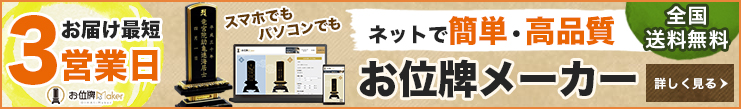位牌が必要になり作ることになったときに、位牌に入れる文字の「書き方」をどうすればいいのか悩んでしまうかもしれません。
仏壇に祀られる位牌は、故人様そのものとされる大切なものです。
この記事では、位牌の正しい書き方やルール、注意点について詳しく解説します。
初めて位牌を作る方は、ぜひ参考にしてください。
位牌とは
位牌とは故人様を象徴するものであり、故人様の霊魂が宿る場所とされています。
なぜ位牌が必要なのか、位牌について詳しく知ることが大切です。
位牌の必要性
位牌には、故人様が仏の世界で名乗ることができる「戒名」が記されています。
位牌は、遺族が仏壇に祀り、故人様が仏の世界に行けるように祈ると同時に、日々供養をするために必要なのです。
位牌には種類がある
位牌は形や色などに決まりがなく自由に選べますが、使う時期や目的によって種類が分かれています。
適した種類の位牌を選ぶ必要があるため、どのような種類があるのかを知っておきましょう。
白木位牌
白木位牌は、葬儀から四十九日までの期間に使う位牌で、「仮位牌」とも呼ばれる位牌です。
戒名や俗名は、手書きで書かれています。
四十九日までに本位牌を準備し、四十九日の法要が終われば、お寺で供養してもらうことが一般的です。
本位牌
四十九日の法要後は、それまでの白木位牌から本位牌に替え、正式な位牌として仏壇に祀ります。
本位牌にはさまざまな素材やデザインがあり、ほとんどの場合は自由に選べます。
地域や宗派によって決まりがある場合があるため、供養する前にお寺に確認すると安心です。
繰出位牌
何人ものご先祖様の位牌を、一つにまとめるための位牌です。
仏壇に置くことができる位牌の数はそう多くないため、複数の位牌を一つにまとめる際に、繰出位牌を使用します。
位牌の上部の蓋の中に複数の札板が収納されていて、故人様一人につき一枚の札板を使って祀ります。
寺位牌
寺位牌とは、お寺で使用する位牌のことです。
位牌は自宅に祀るものですが、自宅で供養できない事情がある場合や、永代供養を希望する場合には、お寺に位牌を置いて供養してもらえます。
もともとは自宅で供養していた場合、自宅に置いていた位牌をそのまま寺位牌として祀ってもらえることもあるので、相談してみてください。
四十九日で魂入れが必要
魂入れとは、新たに購入した位牌などに祀る方の魂を入れることです。
僧侶の読経によって行われ、位牌だけでなく、お墓や仏壇に対しても可能です。
四十九日まで使用する白木位牌は仮の位牌なので、本位牌に替える四十九日の法要で白木位牌から本位牌へ魂を移す必要があり、ここで魂入れを行います。
宗派ごとの位牌の考え方
位牌に対する考え方は、どの宗派もほとんど違いは見られませんが、浄土真宗は異なる点があり、注意が必要です。
仏教と無宗教、浄土真宗それぞれの位牌について解説します。
仏教徒
仏教ではほとんどの宗派で、位牌は故人様の魂が宿る場所と考えられています。
そのため、故人様や家族が仏教徒であれば、位牌を準備するのがおすすめです。
位牌が必要かどうか迷った際には、お寺に相談してみるとよいでしょう。
無宗教
無宗教の場合、位牌は必要ありません。
しかし、故人様をしのび、供養したいと考える場合には、自由に位牌を置けます。
ただし、お寺に属していない場合は戒名を授かるのが難しく、位牌に入れるのは故人様の名前である俗名です。
浄土真宗
浄土真宗では、仏壇に位牌を置きません。
これは、人が亡くなるとすぐに仏になるという教えのためで、仏門に入って仏を目指すほかの宗派と異なるポイントです。
浄土真宗では戒名は存在せず、仏の弟子である証に法名を授かります。
仏壇に位牌を置かない代わりに、過去帳と法名軸を置き、過去帳に法名や俗名、没年月日、没年齢を記します。
法名軸は、仏壇の内側に掛ける浄土真宗だけで使われる仏具で、故人様の法名が記載されます。
位牌の文字について

位牌に入れられている文字は、神聖なものであり、とても大切です。
文字の種類や色、どのようにレイアウトするのがよいのか、費用に関することを解説します。
彫り文字
位牌に入れる文字は、彫り文字が主流となっています。
彫りによる陰影がつくため、文字の輪郭が際立つ美しい仕上がりが、彫り文字のメリットです。
彫り文字は、彫りによる力強い文字と、経年劣化が少ないという特徴があります。
書き文字
位牌に直接文字が入る書き文字は、柔らかく温かみのある印象に仕上がります。
上品さがあり、やさしい雰囲気を演出できることが、書き文字の特徴です。
位牌には彫り文字・書き文字のどちらにしなければならない、という決まりがないため、好みに合わせて選べます。
すでに位牌がある場合は、同じ手法を選ぶとよいでしょう。
位牌の素材で選ぶ方法もあり、鏡面仕上げの位牌であれば書き文字が漆の質感をより生かせます。
木の質感を生かすには、凹凸がある彫り文字がおすすめです。
文字の色
位牌の文字は一般的には金色ですが、決まりがあるわけではないので、文字の色も選べます。
しかし、どの色を選べばいいのかが分からず、困ってしまう方も多いでしょう。
迷ったときには、裏も表も金色を選ぶと無難に仕上がります。
色で気を付けなければならないことは、生前に位牌を作る場合です。
生前に作る位牌の文字は、戒名と俗名の部分を朱色にします。
位牌に入れる文字のレイアウト
位牌のレイアウトは、誰の位牌なのかによって異なります。
一人の場合は中央に戒名が入りますが、夫婦で一つの位牌を作る場合は左右に並べて入れることが可能です。
また、先祖代々を一つの位牌にする場合、個人や夫婦の位牌と異なり、戒名が入りません。
先祖代々の位牌は、表に「○○家先祖代々之霊位」と入れて、裏には何も入れないことが一般的です。
位牌の文字入れ費用はどのようにして決まる?
位牌の文字入れ費用の相場は、3,000円から10,000円程度です。
位牌本体の価格に、文字入れ価格が加算されて価格が決まります。一般的に、文字入れ価格は文字数ではなく、一名分の価格で決まっています。
お位牌Makerでの文字入れは一霊分無料で行っており、二霊分の夫婦連名の場合は3,300円(税込み)となっており、相場よりも安い価格で文字入れが可能です。
また、文字入れは戒名だけでなく、俗名や没年月日なども含まれますが、書き方については次の項で詳しく紹介します。
位牌の基本的な書き方
位牌は、基本的なレイアウトが決まっています。
では、どのような文字が入るのか、位牌の書き方を解説します。
戒名
戒名は、位牌の中央に入れます。
戒名の文字数はさまざまなので、文字数が多い場合は位牌のサイズを文字数に合わせるか、位牌のサイズに合わせて文字のサイズ調整が必要です。
没年月日
故人様が亡くなった没年月日は「命日」と呼ばれる日で、位牌の書き方はさまざまです。
裏面・表面の決まりはなく、関東では表へ、関西では裏へ入れる傾向が見られます。
位牌の表面に入れる場合は、戒名の両側に入れるのが一般的です。
戒名を挟んで右側に亡くなった年を、左に月日を入れます。
故人の名前
故人様の名前は「俗名」といい、位牌の裏面中央に入れます。
戒名だけでは誰の位牌なのか分かりにくいため、生前の名前を入れて、祀られている方を誰が見ても分かるようにしているのです。
亡くなった年齢
亡くなったときの年齢は、位牌の裏面に入れることが多いです。
年齢の前に「行年」や「享年」と記され、満年齢または数え年のどちらかを使用します。
戒名とは
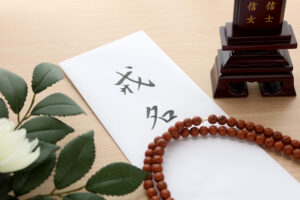
仏様の弟子となり、その証として授けられる名前を「戒名」といいます。
位牌に記されているものですが、戒名について詳しく知っている方は少ないかもしれません。
ここでは、戒名とはどのようなものかを解説します。
戒名の基本的な構成
戒名は、以下の5つによって構成されています。
1. 院号・院殿号
一番上に配置される文字で、これは寺院に貢献した特別な方に授けられるものです。
そのため、一般的な戒名には、院号や院殿号が付いていません。
2. 道号
故人様を表す文字で、生前の仕事や名前などに由来します。
宗派によって「道号」以外の名称で呼ばれることもあるので、注意が必要です。
3. 戒名
道号に続いて記されるものが、戒名です。
一般的に戒名には、生前の名前から一文字取って使われます。
4. 位号
戒名の次に入り、仏教徒としての位を表すものです。
5. 置字
置字は「之霊位」「位」といった、戒名の最後に記される文字です。
必ず必要というわけではなく、省略されることもあります。
戒名のランク付け
仏教では平等が重んじられますが、戒名にはランクが存在します。
ランクはお布施の金額で決まることが多いですが、これはお寺を長く存続させて、先祖の供養をしっかりと続けていくために大切なことなのです。
ランクは、「院号・院殿号」と「位号」に入る文字によって決まります。
それぞれのランクについて見ていきましょう。
男性は「信士→居士→大居士」の順で、女性は「信女→大姉→清大姉」の順でランクが上がっていきます。
戒名に院号や院殿号が加わると、さらにランクが上がる仕組みとなっています。
江戸時代に、大名には院号や院殿号を付け、下層階級には居士や大姉が使えないという身分差別がありました。
つまり、戒名のランク付けは江戸時代の身分差別のなごりなのです。
戒名の文字に関する注意点
戒名の文字を入れる際には、いくつか注意しなければならないことがあります。
戒名の旧字
戒名には、昔の漢字である旧字が使われることがあります。
位牌の文字は、葬儀で使用する白木位牌に記された文字をそのまま書き写すことが一般的です。
旧字を正確に入れるためにも、戒名を口頭で伝えるのではなく、白木位牌を持参してください。
文字色やレイアウトの確認
希望どおりの位牌に仕上げるためには、文字の色やレイアウトを事前に確認しておくことが大切です。
すでに仏壇に位牌がある場合は、文字色やレイアウトをそろえるとよいでしょう。
戒名を入れる手法
位牌に戒名を入れる手法は、機械彫りと手書きの2種類があります。
機械彫りのメリットは、文字が整っておりソリッドな印象を持っていることです。
納期が早いことも機械彫りならではの特徴で、スピード仕上げが可能な場合もあるため、急ぎの場合には相談してみてください。
手書きのメリットは、文字に味わいがあり、柔らかな印象を持っていることです。
完成までに時間がかかりやすく、制作できる仏壇店が限られるため、手書きを希望する場合には注意しましょう。
また、お位牌Makerでは、全45種類以上の豊富なバリエーションのお位牌を、お客様のご要望に沿ってオーダーメイドで作成いたします。
さらに全国対応しており送料無料で、最短翌日にお届けいたします。
故人様を祀る大切なお位牌を、お位牌Makerにご依頼してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせはこちら
戒名がない場合
無宗教の方は戒名がないため、生前の名前である俗名を位牌の表面に入れます。
俗名に続いて「之霊位」とするのが一般的です。
通常では本位牌に「之霊位」とは入れず、「位」を用います。
しかし、戒名がない場合には「之霊位」が使われるのです。
位牌の表に俗名と没年月日が、裏には亡くなった年齢が記載されます。
「位」や「霊位」の書き方

位牌に「位」や「霊位」の文字が入っていることをなんとなく見たことがある、という方は多いです。
しかし、それらの違いや意味については、あまり知られていません。
「位」「霊位」について、詳しく解説します。
「位」「霊位」とは
本位牌の戒名の後には、一般的に「霊位」は入れず、「位」の文字を入れることがあります。
そもそも「位」や「霊位」は、下文字(したもじ)と呼ばれ、生前の地位を示すために使われていたものです。
身分制度のなごりとして使われているため、現代ではあまり意味のないものといえます。
最近では、「位」「霊位」が使われないことも多いです。
すでに仏壇に先祖の位牌がある場合には、同じようにそろえて作るケースもあり、作る際にはお寺に確認するとよいでしょう。
初めて位牌を作る場合の書き方
初めて位牌を作るときには、お寺に相談すると間違いがなく安心です。
インターネットで位牌に関する情報を調べられますが、宗派による違いだけでなく、地域による違いもあります。
また、「〇〇宗の場合は『位』を使わない」とされている場合でも、地域によっては使うことがあるために注意が必要です。
例外が多いため、初めて位牌を作るときはお寺に確認してから注文しましょう。
本位牌の場合の書き方
葬儀の際には白木位牌を使いますが、白木位牌と本位牌では、書き方に違いがあります。
白木位牌には、戒名の後の置き字として「霊位」が入りますが、本位牌には「霊位」を使いません。
故人様は四十九日を迎えると、仏門に入るといわれています。
仏門に入るということは、仏様の世界に行くことを意味するため、「霊位」が使われなくなるのです。
「霊位」が使われない本位牌では、「霊位」に代わり「位」が使われますが、近年では「位」も使わないケースが増えてきています。
すでに位牌がある場合の書き方
先祖代々の位牌がある場合も、まずは故人様一人の位牌を作ることが一般的です。
33回忌または50回忌のタイミングで、一人の位牌から先祖代々の位牌へと魂を移します。
また、先祖代々の位牌以外に個別の位牌が仏壇にある場合、統一感も大切です。
戒名の書き方や位牌全体のレイアウトをそろえると、全体の調和が取れます。
年齢の書き方

位牌に入れる年齢の書き方に決まりはありません。
ただし、決まりはないものの一般的な書き方があり、日常生活の中での年齢表記とは異なる点も多いため、ぜひ知っておいてください。
「享年(きょうねん)」と「行年(ぎょうねん)」
位牌に記載する年齢には、数字の前に「享年」または「行年」と入れます。
「享」の文字は「授かる」という意味を持ち、天から授かった命の年数のことをいいます。享年とは亡くなった年齢であり、一般的に数え年での年齢です。
一方で行年は、この世に生まれてから修行を行った年数である、満年齢を表します。
「数え年」と「満年齢」
年齢の数え方には、数え年と満年齢の2種類があり、これは位牌のためのものではなく、広く一般的に使われているものです。
今日では、満年齢が一般的な年齢の数え方とされているため、数え年を知らない方も多いでしょう。
位牌を作るときには、数え年と満年齢について知っておかなければ、混乱してしまう可能性があります。
数え年と満年齢がどのようなものなのか、分かりやすく解説します。
数え年
数え年は誕生した日に1歳として始まり、誕生日とは関係なく、毎年1月1日に年齢が1歳上がります。
メリットは、誰もが同じタイミングで年齢を重ねるので、分かりやすいことです。
しかし、12月31日に生まれると、翌日には2歳になってしまいます。
また誕生日によって、実際に生きてきた年月の長さと大きく差が出てしまうデメリットがあります。
数え年は、1950年に年齢の数え方が法律で変わるまで使われていました。
満年齢
満年齢は、一般的な年齢の数え方として、現在使われている方法です。
誕生した日に0歳から始まり、次の誕生日に年齢が1歳上がります。
「歳」と「才」の違い
位牌に年齢を入れる場合、年齢の後に「歳」または「才」の文字を入れます。
2つの文字は、どのような場合にどちらの文字を使用する、という決まりはなく、どちらでも自由に使えます。
しかし、「歳」と「才」は意味に違いがあるため、意味で選ぶのもよいでしょう。
「歳」は年齢のほか、1年や年月といった意味があり、「才」は持って生まれた能力、物事を成し遂げる能力といった意味を持ちます。
位牌の書き方で注意すべきポイント

位牌といっても、どのような方の位牌なのかによって、書き方はさまざまです。
作るタイミングによって、書き方に違いが生じることがあるため、気を付けなければなりません。
ここでは、位牌の書き方で気を付けたい、5つのポイントを紹介します。
生前位牌
生前位牌とは、亡くなる前に作る位牌のことをいいます。
一般的に位牌は、亡くなった後で作るものです。
しかし、亡くなる前に戒名をもらい、位牌を作ることも可能であり、位牌の書き方にも特徴があります。
生前位牌では、戒名を入れる文字の色が赤色です。
生きている間に位牌を作るため、没年月日と亡くなる年齢は空欄にしておきます。
生前位牌といっても、亡くなった後には一般的な位牌となるため、基本的な書き方に違いは見られません。
亡くなると、戒名の文字色を金色に直し、没年月日と没年齢を入れます。
夫婦連名の位牌
夫婦で一つの位牌を作ることも可能で、「夫婦(めおと)位牌」と呼ばれます。
戒名を並べて入れるバランスを考え、位牌のサイズを選ばなければなりません。
夫婦位牌の書き方は、特に決まりはなく、いくつかのパターンに分かれます。
人気なのは、表面の右側に夫、左側に妻の戒名を入れ、裏面の右側に夫、左側に妻の俗名を入れる方法です。
没年月日は表面に、没年齢は裏面に入れるのが一般的です。
子どもの位牌
未成年の場合、位牌の書き方が異なるため、注意が必要です。
また、未成年の中でも、さらに年齢によって違いがあります。
年齢 位牌に入れる文字
死産 水子(すいじ)
1歳未満 嬰子(えいじ)・嬰女(えいにょ)
3歳未満 亥子(いのこ)・亥女(かいじょ)
18歳未満 童子(どうじ)・童女(どうじょ)
上記の表は一般的なものなので、宗派によって異なる場合があり、位牌を作る前にお寺に確認してください。
特定の宗派を持たない場合の位牌
戒名は仏門に入った証として、お寺で授けられます。
特定の宗派を持たない場合は戒名を授からないため、位牌には戒名が入りません。
戒名がない位牌は「俗名位牌」として、生前の名前である俗名の下に「之霊位」を付けます。
通常では本位牌に「之霊位」や「霊位」は入れませんが、特定の宗派がなく戒名がない場合には入れることが一般的なのです。
地方や宗派によって異なる
今回は、一般的な位牌の書き方についてご紹介していますが、地方や宗派によって異なることがあり、注意が必要です。
地方による違いとして、関東・東海・関西では、微妙な違いが見られます。
例えば、一般的に没年月日は位牌の表面に記載しますが、関西では裏面に書かれることが多いです。
宗派によって異なる点は、戒名に入れる文字の違いや、位牌のレイアウトの違いだけではありません。
浄土真宗では、教義により「南無阿弥陀仏」と唱えることで極楽浄土に導かれるとされているため、位牌は不要とされているのです。
地方や宗派による違いは、お寺に確認してください。
まとめ
今回は、位牌の書き方を紹介しました。
位牌の書き方について詳しく知らなくても、お寺や仏壇店に聞けば教えてもらえるので、難しく考えなくても問題はありません。
しかし、位牌は亡くなった方を供養する大切なものなので、位牌に書かれている内容や意味を知っておくとよいでしょう。