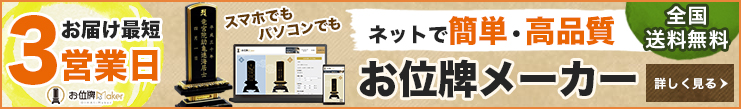「仏壇がないので、位牌をどこへ置けばいいのか分からない」という方はいませんか?
この記事では、仏壇のある場合とない場合の位牌の置き方について解説します。
位牌が複数ある場合の並べ方についても解説しているので、位牌の置き方や並べ方で悩んでいる方は参考にしてください。
位牌を置く前にやるべきこと
位牌の置き方を知る前に、やるべきことについて解説します。
四十九日までは後飾りに安置する
葬儀が終了したら、納骨を行う四十九日法要まで、自宅の後飾り祭壇に位牌と遺骨を一時的に祀ります。
後飾り祭壇は、故人の冥福を祈るために弔問客が参拝する場所です。
地域によっては、中陰壇(ちゅういんだん)や自宅飾りと呼ばれることもあります。
後飾り祭壇は、仏壇がある場合は仏壇の前に設置します。
仏壇がない場合は、自宅の北側に位置する部屋か、西側に位置する部屋に設置してください。
直射日光の当たる場所や湿気が多い場所は、遺骨を傷めてしまうので避けるようにしましょう。
四十九日法要のタイミングで開眼供養を行う
位牌を自宅に安置するためには、新しい位牌に故人の魂を宿らせる目的で行われる開眼供養の儀式が必要です。
開眼供養は入魂式や魂入れと呼ばれることもあります。
開眼供養は、納骨が行われる四十九日法要の際に行うケースが多いです。
開眼供養を行うためには、菩提寺の僧侶への依頼が必要になります。
地域やお寺によってマナーやルールが異なるため、分からないことは事前に問い合わせておきましょう。
仏壇がある場合の位牌の正しい置き方

位牌は仏壇に置くのが一般的です。
自宅に仏壇がある場合の位牌の置き方について解説します。
一般的な位牌の置き方
位牌を仏壇に置くときの重要なポイントは、次の3つです。
● 位牌はご本尊よりも1つ下の段に置く
● ご先祖様は右側(上座)から並べる
● ご本尊や両脇が隠れないようにする
位牌を置く位置は、ご本尊様が置いてある段の1つ下の段になります。
上段は上座であり、上座に祀るのはご本尊様のみです。
信仰する宗派のご本尊は、上座の中央に設置します。
上段に加えて、右側も上座と考えましょう。
そのため、仏壇に向かって右側にはご先祖様を置き、目上の方から順番に左側へ祀っていくことになります。
また、ご本尊様の両脇には掛け軸がありますが、1段下に位牌を置くと顔が隠れてしまうことがあり、失礼にあたってしまいます。
その場合は、位牌をもう1段下に置くか、顔が隠れない位置に調整して置くようにしましょう。
仏壇内部の段数が少ない場合
段数が少ない仏壇の場合は、置ける位牌の数が2本までと決まっています。
仏壇の右側が上座となるため、ここに回出位牌や先祖位牌を設置してください。
2本目の位牌は、下座となる左側に置きます。
位牌のサイズですが、1本目の位牌よりも総高が大きくならないようにしましょう。
仏壇内部の段数が多い場合
段数が多い仏壇の場合、置ける位牌の数は4本までです。
位牌の右側が上座になるため、1本目は2段目の右側に設置します。
2本目は下座にあたる2段目の左側、3本目は3段目の右側、4本目は3段目の左側です。
位牌のサイズは、2本目は1本目、3本目は2本目、4本目は3本目よりも総高が大きくならないように配慮しましょう。
仏壇がない場合の位牌の置き方
住宅事情や宗教、管理負担などの理由から、仏壇を置かない家も増えています。
仏壇がない場合の位牌の置き方をチェックしていきましょう。
仏壇なしでも問題はない
仏壇がないからといって、位牌を置くために新しく購入する必要はありません。
故人やご先祖様を偲ぶ気持ちが大切になります。
仏壇なしで位牌を祀っても問題がないケースは、次のとおりです。
● 信仰している宗教がない場合
● 分家の場合
● 仏壇を置くスペースがない場合
● 仏壇を用意する余裕がない場合
しかし、お寺の住職から戒名を授かっている場合は、基本的に仏壇に位牌を祀る形になります。
仏教徒の場合は、お寺の代わりとなる仏壇に、ご本尊と位牌を置いて供養しましょう。
位牌が傷みにくい場所に置く
仏壇がない場合は、木製の位牌が傷みにくい場所に設置しましょう。
風通しがよく、家族が集まりやすい場所が適しています。
位牌を置くのに適している場所は、次のとおりです。
● リビング
● 寝室
● 和室
● 床の間
なお、直射日光が当たる場所や高温多湿になりやすい場所は、位牌を置くのに適していません。
来客の目につきやすい玄関や、キッチンなどの水回りに設置するのも避けましょう。
位牌の飾り方
仏壇なしで位牌を飾る場合のポイントは、次のとおりです。
● 直置きせず棚を用意する
● 飾り棚を利用する
● ミニ仏壇を用意する
仏壇ではない場所への位牌の飾り方について詳しく解説します。
直置きせず棚を用意する
見下ろせる位置ではなく、棚やチェストなど腰くらいの高さのある場所に位牌を置いてください。
座って手を合わせるときに、目の高さになるくらいの高さが目安です。
故人の魂が宿っている大切なものなので、直置きにならないように清潔な布を敷きます。
位牌のほかに、ご飯や水をお供えできるスペースも確保しましょう。
飾り棚を利用する
部屋の中にスペースがない場合は、壁掛けの飾り棚を使って、位牌を置くスペースを作ることもできます。
シンプルなので、和室にも洋室にもマッチします。
位牌のほかに、季節に合った花や故人の写真、装飾品を飾ってもよいでしょう。
ミニ仏壇を用意する
棚や飾り棚に置きたくない場合は、コンパクトで場所をとらないミニ仏壇を活用する方法もあります。
ミニ仏壇とは、棚の上に置ける小さなサイズの仏壇のことです。
マンションやアパートなど、仏壇を置くスペースがない住居に住んでいる方でも、スペースを有効に活用できます。
さまざまなデザインのミニ仏壇が販売されているので、部屋の雰囲気に合わせて選んでみましょう。
位牌が複数ある場合の並べ方

位牌が増えて、仏壇に置けなくなってしまった場合は、どう対応すればよいのでしょうか。
ここでは、位牌が複数ある場合の並べ方について解説します。
先に亡くなった方から順に並べるのが基本
位牌を設置する順番は、先に亡くなった方を右側の上座に置き、後に亡くなった方を左側の下座に置くという並びです。
置ききれなくなった場合は、1段下の右側、左側という順番で置いていきます。
また置ききれなくなった場合は、さらに1段下の右側、左側という順で設置します。
先に亡くなった方が上座になる理由
仏教には、亡くなった方が仏弟子として新しい名前(戒名)を授かり、仏様のもとで極楽浄土へ行くための修行をするという教えがあります。
先に亡くなられた方は長く修行を積んでいるため、位が高いと判断されるのです。
先祖位牌は上座に置く
先祖代々の位牌を一つにまとめた先祖位牌がある場合は、すべての位牌の上座となる右側の2段目に設置します。
戒名が書かれた位牌を一つにまとめた繰出位牌がある場合も、2段目右側に置くのが基本です。
もしも、先祖位牌と繰出位牌の両方がある場合は、先祖位牌が2段目右側、繰出位牌が2段目左側になります。
通常の位牌の設置場所は、その1段下の右側からになります。
位牌を一つにまとめる方法もある
位牌が増えて仏壇に置ききれなくなってしまった場合は、先祖位牌や繰出位牌といった複数の位牌を一つにまとめる方法が選択できます。
繰出位牌の中には、10枚程度の木札を入れることが可能です。
木札には故人の戒名や没年月日が記されています。
複数の位牌を繰出位牌に移動させたい場合は、菩提寺の住職に相談してください。
地域や宗派によって、位牌を移すタイミングが決められている場合があります。
仏壇が狭くなってきたら、位牌を一つにまとめることを早めに検討しましょう。
位牌の置き方に関するよくある質問
最後に、位牌の置き方に関するよくある質問に回答していきます。
位牌の宗派が異なる場合の置き方は?
継承者がいないなどの理由から、宗派の異なる位牌が2つある場合、仏壇を2つ置いて祀る必要があります。
しかし、お寺や地域によっては、「同じ宗派でも別のお寺から授かった戒名の位牌を、同じ仏壇に置いてはいけない」としている場合があるので注意してください。
また、お寺に相談せずにまとめてしまうと、トラブルが発生する可能性もあります。
子どもの位牌の置き方は?
親よりも子どもが先に亡くなり、後から親が亡くなってしまった場合は、親を上座の右側、子どもを下座の左側に置くこともあります。
先に亡くなった方から上座に置く、というルールが適用されないので気を付けましょう。
なお、置き方の順番が分からない場合は、お寺の住職に相談すると安心です。
位牌を置く向き(方角)に決まりはある?
位牌を置く向きや方角に関して、明確なルールは定められていません。
ただし、宗派によっては向きが決まっている場合もあります。
日当たりがよい場所や湿気が多い場所は置く場所に向かないので、直射日光が当たらない向きや風通しがよい向きなど、条件を考慮した上で決めましょう。
不要になった位牌の置き場所は?
位牌を一つにまとめたことにより、不要になった位牌がある場合は、「閉眼供養」や「魂抜き」と呼ばれる儀式を行う必要があります。
位牌の閉眼供養は、繰出位牌の開眼供養の儀式と同時に行うのが基本です。
不要な位牌は儀式の終了後に住職に引き渡しを行い、お焚き上げという形で供養します。
まとめ
今回は、位牌の置き方について解説しました。
ご本尊は各宗派の信仰対象となるため、仏壇の最上段に設置するのが決まりです。
位牌は、ご本尊の1段下に置きます。
ご先祖様の位牌は上座となる右側から置いていきます。
位牌が増えて置けなくなってしまったら、位牌を一つにまとめる繰出位牌を選択しましょう。
仏壇がない場合でも、位牌を安置することができます。
お位牌Makerでは、全45種類以上の豊富なバリエーションのお位牌をお客様のご要望に沿い、オーダーメイドで作成いたします。
さらに全国対応しており、送料無料で、最短翌日にお届けいたします。
故人様を祀る大切なお位牌をぜひ、お位牌Makerにご依頼してみてはいかがでしょうか。
位牌を置くのに適した場所に位牌を置いて、故人やご先祖様を偲びながら手を合わせましょう。