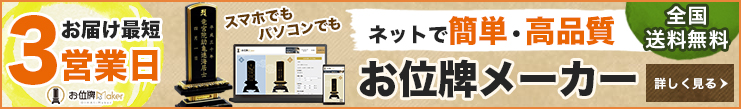本位牌とは、故人の霊を祀るために使われる大切な供養具です。
本位牌にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴や使い方が異なります。
しかし、初めて準備する際は種類が多く、どれを選べば良いのか悩む方も少なくありません。
本記事では、本位牌の基本的な役割や種類、選ぶ際に押さえておきたいポイントをわかりやすく紹介しています。
本位牌について深く知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
本位牌とは?必要性と位牌の種類
位牌は、故人の魂を祀るための重要な仏具で、故人との繋がりを感じながら供養を行うために使用されます。
ここでは、位牌の種類やそれぞれの役割、また「本位牌」の必要性について詳しく解説します。
まずは、位牌の基本的な役割を理解した上で、「本位牌」と「白木位牌」の違いや、それぞれの使用方法について確認していきましょう。
そもそも位牌とは?
そもそも位牌とは、故人の魂が宿るもしくは戻ってくる場所と考えられています。
そのため、故人を供養するうえで、とても大切に扱われています。
現在の日本の仏教において、位牌は葬儀や法事などで用いられますが、もともとは中国から取り入れたものと言われています。
位牌には、故人がいつ亡くなったのか、誰の位牌なのかがすぐわかるように、故人の戒名や没日、生前の名前などが記載され、仏壇や祭壇にお祀りされます。
「本位牌」は四十九日法要以降に使う位牌
本位牌は、故人が亡くなってから四十九日目の法要以降に使用される位牌です。
本位牌を使用する前の故人の魂は、「白木位牌」と呼ばれる仮の位牌に宿っており、四十九日目の法要を境に本位牌へ移されます。
これは、亡くなった方の魂は四十九日まであの世とこの世を行ったり来たりし、四十九日目に極楽浄土へ到着し、その後の行き先が定められると言われているからです。
つまり、四十九日法要は故人にとって非常に重要な日となり、この日に本位牌へ魂が移ることで、故人への大切な供養となるのです。
また、本位牌には、素材や加工方法が異なるいくつかの種類があります。
「白木位牌」は四十九日まで使用する仮の位牌
白木位牌は、故人が亡くなってから四十九日まで使用する位牌のことで、仮位牌ともよばれます。
また、白木位牌には「内位牌」や「野位牌」の2種類の位牌があり、それぞれ使用方法が異なります。
内位牌は、自宅に保管する用の位牌で、仏壇や祭壇に祀られます。
基本的には、四十九日法要の際に本位牌へ移されますが、そのまま使用されるケースもあります。
野位牌は、お墓で使用されたり、葬儀後に故人とともに火葬されたりします。
場合によっては、お焚き上げもしくはお寺に納められることもあります。
白木位牌から本位牌へ移す際は「閉眼供養」と「開眼供養」が必要
白木位牌から本位牌へ移行するタイミングは、四十九日法要のときです。
その際、白木位牌から魂を抜き取るために必要な「閉眼供養(魂抜き)」と、本位牌へ魂を入れる「開眼供養(魂入れ)」が必要です。
「開眼供養」で故人の魂を移すことで、初めて供養するためのものとなります。
そのため、閉眼供養と開眼供養は、故人の魂を正しく位牌に宿すために欠かせない重要な儀式となります。
本位牌は素材や使用方法によって種類が異なる

本位牌には複数種類があり、素材や加工、使用方法によって選べるものが異なります。
ここからは、本位牌の種類について紹介していきます。
素材や使用方法を理解し、適切なものを選びましょう。
素材による本位牌の種類
本位牌の素材には、以下のものがあります。
- 唐木位牌
- 塗位牌
- モダン位牌
- 天然木位牌
それぞれの特徴を紹介していきます。
唐木位牌
唐木位牌は、重量感や光沢のある黒檀や紫檀といった木材を用いて作られた位牌です。
非常に硬い素材で、虫や金などの影響を受けにくい耐久性が高い特徴を持っており、仏壇にも使用される高級木材でもあります。
また、シンプルな見た目も特徴のひとつで、木目を活かして透明の装飾が施されており、仏壇にも合わせやすい位牌です。
塗位牌
塗位牌は、ヒノキなどで作られた木の札の上から、漆を施した黒い見た目が特徴の位牌です。
また、塗位牌には金粉や金箔、金色の塗料が使用された装飾が施された位牌もあります。
基本的に黒色のものが多いですが、いくつかの仕上げ方法があり、種類によって価格が異なってきます。
モダン位牌
モダン位牌は、クリスタルや陶器、銘木、天然石などを使用して作られる位牌です。
伝統にとらわれない素材や加工方法を用いた、自由なデザインができるところが特徴です。
モダンな仏壇に取り入れられることが増えてきており、近年人気の出てきた位牌といえます。
天然木位牌
天然木位牌は、その名の通り天然の木を用いて作られた位牌です。
具体的な素材は、ヒノキや桜などの木材が使用されます。
天然木位牌は、天然木の特徴であるナチュラルな色合いが特徴で、唐木位牌より自然本来の見た目や風合いを活かしたデザインが魅力です。
使い方による本位牌の種類
使い方による本位牌の種類には、以下のものがあります。
- 板位牌
- 寺位牌
- 繰り出し位牌(回出位牌)
こちらも詳しく解説していきます。
板位牌
板位牌は、その名前の通り板状の形をしており、板が台座に立てられた形状をしている位牌です。
「札位牌」ともよばれ、故人に合わせて個別に用意されます。
寺位牌
寺位牌は、何らかの事情により位牌を自宅に置けない方が、代わりにお寺や菩提寺で供養してもらうための位牌です。
江戸時代以前では多く見られていましたが、自宅に位牌を置く方が増えるにつれ、少なくなってきました。
寺位牌は、通常の位牌より大きいのが特徴です。
ただし、お寺の保管場所によってはサイズの合わない位牌もありますので、使用する場合は事前に確認するのが良いでしょう。
繰り出し位牌(回出位牌)
繰り出し位牌は、複数の本位牌をまとめてひとつの位牌にするときに用いられる位牌です。
回出位牌ともよばれ、主に仏壇に先祖の位牌が多くなってきた際に使用されます。
箱型の形状をしており、複数の位牌を積み重ねて収納できる構造になっています。
収納可能な位牌の数は、サイズにもよりますが、およそ10枚前後の場合が多いです。
また、本位牌から繰り出し位牌に移すタイミングは、33回忌もしくは50回忌の弔い上げの際に行われます。
その他の本位牌の種類
そのほかの本位牌の種類には、以下のものがあります。
- 順修牌
- 逆修牌(寿牌・予修牌・生前位牌)
- 過去帳・法名軸
こちらも詳しく解説していきます。
順修牌
順修牌は、亡くなった後に戒名を授かった人のために作られる位牌です。
白木位牌はお寺の住職が用意しますが、順修牌は故人の家族や親族が用意します。
逆修牌(寿牌・予修牌・生前位牌)
逆修牌は、生前に戒名を授かった人のために作られる位牌です。
別名、寿牌・予修牌・生前位牌などとよばれ、夫婦位牌にも使用されることの多い位牌です。
逆修牌に記載される戒名の文字は、通常の位牌と異なる朱色で記載されますが、その方が亡くなった後に取り除かれます。
過去帳・法名軸
過去帳や法名軸は、位牌を用いない宗派である「浄土真宗」の場合に使用されるものです。
浄土真宗は、「亡くなった方の魂は、亡くなった瞬間に極楽浄土へ向かう」という考えのもと、位牌を使用しません。
その代わりに過去帳や法名軸に戒名(浄土真宗の場合は法名)を記載し、仏壇に祀られます。
本位牌は宗派によって戒名(法名)の入れ方が違う

本位牌は、宗派によって少し異なる部分はあるものの、基本的には故人の戒名(法名)、没年月日、俗名などを刻む点では共通しています。
ただし、戒名(法名)の表記方法や文字の配置、さらには使われる言葉や書体などが宗派ごとに異なる場合があります。
ここでは、戒名(法名)とは何かを解説し、それぞれの宗派が記載する戒名の特徴を紹介します。
戒名(法名)とは?
戒名や法名とは、亡くなられた故人が付けられる名前のことです。
一昔前の仏教の考えでは、「仏様の戒めを受け、仏門の世界に出家したものだけに授けられる名前」でした。
そのため、基本的に生前出家された方のみが授けられる名前だったのです。
しかし、現在では「亡くなった方はすべて仏門に入り、戒律を守りながら修行する」という考えに変わり、仏教方式で葬儀を行うすべての方に戒名が授けられます。
なお、この考えはほかの仏教国では見られておらず、日本特有の文化といえます。
浄土真宗
浄土真宗は、先述したように位牌を使用せず、代わりに法名軸や過去帳を用いるのが一般的です。
また、浄土真宗は、ほかの宗派と考え方が異なり「出家せず阿弥陀仏の教えを守りながら生きていく」ことを誓うために法名が授けられます。
法名の書き方は、男性が「◯◯院釋◯◯」、女性が「◯◯院釋尼◯◯」と、女性の方に「尼」の文字が記載される違いがあります。
浄土宗
浄土宗は、通常の位牌を用いて故人を供養します。
浄土宗の戒名の書き方は、「誉」の字を記載することがほとんどです。
男性であれば「◯◯院◯誉◯◯居士(信士)」、女性であれば「◯◯院◯誉◯◯大姉(信女)」と記載します。
また、戒名の上に梵字を記載しますが、これは阿弥陀如来を意味する「キリーク」という文字のことです。
真言宗
真言宗も、浄土宗と同様に通常の位牌を用いて故人を供養します。
真言宗の戒名の書き方は、戒名の上に記載する梵字に「ア」と書くことが多いです。
これは、院号が付くケースでは増える場合があります。
男子ではアの梵字の下に「◯◯院◯◯居士位(信士)」、女性ではアの梵字の下に「◯◯院◯◯大姉位(信女)」と記載されます。
日蓮宗
日蓮宗も、浄土宗や真言宗と同様に通常の位牌を用いて故人を供養します。
日蓮宗の戒名の書き方は、「◯◯院」といった院号、「日◯」といった日号、さらに男性と女性、年齢で異なる「信士・居士」や「信女・大姉」が記載されます。
また、戒名の上に記載する文字に「妙法」と書く場合も多いです。
具体的には、男性で「◯◯院◯◯日◯◯居士(信士)」、女性では「◯◯院◯◯日◯◯大姉(信女)」と記載します。
禅宗(曹洞宗・臨済宗)
禅宗もほかの宗派と同様に通常の位牌を用いて故人を供養します。
禅宗に記載する戒名の特徴は、文字数が6文字となることです。
しかし、「院号」が付く場合は6文字以上となるケースもあります。
記載方法は、男性で「◯◯院◯◯居士(信士)」、女性で「◯◯院◯◯大姉(信女)」と書きます。
本位牌を選ぶポイント

種類のところで紹介したように、本位牌はさまざまな素材や加工方法のものがあります。
そのため、適切な選び方が大切です。
ここでは、本位牌を選ぶポイントと購入できる場所を紹介していきます。
故人の人柄に合わせて選ぶ
本位牌は、故人のために永く使用していくものなので、故人らしさがある位牌がおすすめです。
デザインに決まりはありませんが、故人の人柄に合わせて選ぶのが良いでしょう。
位牌の素材やデザインをチェック
種類については前述しましたが、本位牌にはさまざまな素材やデザインがあります。
故人や仏壇の雰囲気に合わせるのはもちろん、予算も考慮しながら選ぶと良いでしょう。
また、位牌は永く使用していくものなので、耐久性を考慮することも大切です。
使用用途に合わせて選ぶ
本位牌は、使用用途によって選べる種類が異なります。
種類のところで紹介した位牌を確認しながら、用途にあったものを選びましょう。
位牌と仏壇のサイズを確認
本位牌を選ぶ際は、特に位牌と仏壇のサイズをチェックすることを忘れないことが大切です。
位牌も仏壇もさまざまなサイズがありますが、仏壇は基本的にサイズを変えることが難しいです。
そのため、位牌を選ぶ際は仏壇に合わせて購入しましょう。
なお、お子様のための位牌である水子位牌は、小さめのものと決まっていますので、覚えておきましょう。
どのような文字にするのか確認
本位牌に記載する戒名の文字は、宗派によって異なります。
間違った文字入れをした場合の修正依頼は、もちろん費用がかかってきます。
故人がどの宗派なのか、使用する文字はあっているのかしっかり確認してから依頼しましょう。
予算に合わせて選ぶ
位牌は、使用される素材や加工方法によって、費用が大きく変わってきます。
故人を想い高級な位牌も良いですが、予算を超えてしまうと、後々の負担になりかねません。
大切なのは、無理のない範囲で故人への想いを込められる位牌を選ぶことです。
素材やデザインの選択肢は豊富にあるため、仏具店や専門家に相談しながら、自分たちの状況に合ったものを見つけましょう。
本位牌を購入できる場所
本位牌が購入できる場所についても確認しましょう。
本位牌が購入できる場所は、次の3つです。
- 葬儀社
- 仏壇仏具店
- インターネット通販
それぞれの特徴を解説していきます。
葬儀社
葬儀社は、葬儀のほかに本位牌も購入できる業者です。
そのため、葬儀を依頼する際に白木位牌や本位牌の用意もまとめてやって欲しい方におすすめです。
また、忙しい方や位牌にこだわらない方にも良いでしょう。
仏壇仏具店
仏壇仏具店は、葬儀や法事で使用する仏壇仏具を専門に取り扱っている業者です。
取り扱っている位牌の数が多いところが特徴で、故人にあった位牌が見つけやすいです。
また、知識が豊富なスタッフが在籍しているので、悩んだり困ったりしても気軽に質問できるでしょう。
インターネット通販
最近では、インターネット通販でも位牌は手に入れられます。
インターネット通販のメリットは、豊富な種類や予算から位牌を選べることです。
また、サイトによってはオーダーメイドで作成してくれるところもあります。
ただし、実物を見られないので、イメージと異なる仕上がりになる可能性があります。
また、安すぎるものは品質に問題がある場合や偽物の場合があるため、購入先の評判やレビューをよく確認することが大切です。
お位牌Makerでは、全45種類以上の豊富なバリエーションのお位牌をお客様のご要望に沿い、オーダーメイドで作成致します。
さらに全国に対応しており、送料無料で最短翌日にお届けいたします。
故人様を祀る大切なお位牌をぜひ、お位牌Makerにご依頼してみてはいかがでしょうか。
本位牌の価格の目安
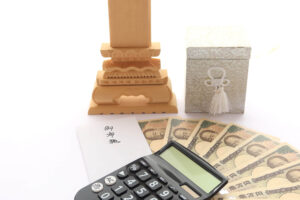
本位牌は、豊富な素材や加工方法があり、選ぶものによって価格は大きく変わります。
ここでは、3つの本位牌の価格を紹介します。
唐木位牌は2万円〜7万円程度
唐木位牌は、黒檀や紫檀などの高級な素材が使われることから、価格は2万円〜7万円が目安です。
ただし、黒檀や紫檀の中にもいくつか種類があり、見た目が美しいものほど価格は上がります。
また、彫刻などの装飾が施される場合は、さらに価格が上がるでしょう。
塗位牌は4万円~10万円程度
塗位牌は、加工や装飾にかかる工程数が多いことから、価格は4万円〜10万円程度が目安です。
しかし、塗位牌は本漆と合成漆のどちらにするかによって価格が大きく異なります。
本漆は、下地塗り、中、上塗りを何度も行った後に、研ぎと磨きの工程が必要なので、合成よりも価格は高くなる傾向です。
一方、合成漆は本漆よりも工程数が少なく、その分価格は1万円程度になる場合もあります。
モダン位牌は3万円~10万円程度
モダン位牌は、自由なデザインを施せることから、価格幅は広く3万円〜10万円が目安です。
使用される素材には、クリスタルや天然石、メープルなどがあり、故人の人柄にも合わせやすい特徴を持っています。
そのため、自由度が高い分価格の幅も広く、使用する素材や加工方法によって大きく変わってくるでしょう。
本位牌を用意する際の注意点
本位牌は、永く使用していくため、1度購入すると買い替えがききにくいです。
そのため、慎重に選ぶことが大切です。
ここでは、本位牌を用意する際の注意点について紹介します。
文字入れの料金は別料金となることがある
本位牌を用意するときに気をつけたいのが、文字入れの料金です。
通常、位牌へ文字を入れる場合、料金やお布施が必要となってきます。
文字の入れ方や購入先によって料金が変わってくるため、事前に確認しておくのが良いでしょう。
なお、一般的な文字入れの料金は、200円〜300円程度となっています。
ただし、文字数によって値段が変わってきますので注意しましょう。
文字が正しく入っているか必ずチェックする
位牌への文字入れは料金がかかってきますが、文字が間違っている場合の修正にも費用がかかってきます。
そのため、文字入れを依頼する前、位牌を受け取った後は、必ず文字が正しいかを確認することが大切です。
文字が間違った位牌のまま葬儀や法要で使用すると、故人に失礼になってしまうため、必ず確認しましょう。
開眼供養(魂入れ)を忘れずに実施する
本位牌を使用する際は、白木位牌から本位牌への「閉眼供養(魂抜き)」と「開眼供養(魂入れ)」が必要です。
なお、閉眼供養と開眼供養は、四十九日法要の際に行われるのが一般的です。
心配な方は、菩提寺に確認しておくと安心できます。
浄土真宗の場合位牌は不要
浄土真宗は、基本的に位牌を使用しません。
浄土真宗は、位牌を使わない代わりに「法名軸」や「過去帳」を使用しますので、間違って位牌を購入しないように、事前に故人の宗派を確認しましょう。
本位牌を作らないケースもある
先ほど紹介しましたが、浄土真宗では本位牌を必要としていません。
また、キリスト教などの仏教徒でない場合も位牌は作りません。
さらに、近年では宗教や慣習にとらわれずに供養を行う家庭も増えており、位牌を作らないケースも見られます。
しかし、位牌を作るかどうかは宗派の教えや家族の意向によるため、必要なのか迷った際には僧侶や専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
本記事では、本位牌の必要性や種類、選ぶポイントを紹介しました。
本位牌は、故人を供養し続けるために欠かせない大切な仏具です。
その種類やデザインはさまざまで、予算や宗派、家庭の事情に合わせて選ぶことが大切です。
また、位牌を選ぶ際は、素材やデザインだけでなく、信頼できる購入先を見極めることが重要です。
故人を想う心を大切にしながら、家族と相談して最適な位牌を選んでください。